Copyright (c) hiraizumi kankou All Rights Reserved.
芭蕉・曽良と奥の細道観光コース
 コース内容と所要時間
コース内容と所要時間芭蕉・曽良が平泉を訪れたコースです。
所要時間は徒歩時速3kmで表示・見学時間は含まれていません。
歩いて見学時間を含めるとおおよそ5,6時間前後でしょうか、、
| 平泉駅 | 0.7km 14分 |
伽羅御 所跡 |
0.1km 2分 |
柳之御 所跡 |
0.5km 10分 |
無量光 院跡 |
| 0.1km 2分 |
||||||
| 経蔵 | 0.1km 2分 |
中尊寺 金色堂 |
0.7km 14分 |
衣の関 | 0.9km 18分 |
高館 義経堂 |
| 0.1km 2分 |
||||||
| 白山 神社 |
3.2km 64分 |
平泉駅 |
松尾芭蕉と曽良
素朴な疑問として芭蕉はなぜ平泉を目指したのだろうかと思う。西行法師に憧れて彼の旅した奥州へ足を踏み入れたかったからなのか、、、 栄華を誇った藤原三代と田野に変わり果てしまった今、世のはかなさは芭蕉の文学的興味そのものを刺激したからなのか、、、
そして悲劇の英雄義経との関わりあい。・・・・???だ。
「奥の細道」は芭蕉の著作中で最も著名な「月日 は百代の過客にして…」という序文により始まり、日本の古典紀行文では最も代表的な作品です。 以下の句以外にも作品中に多数の俳句が詠み込まれています。
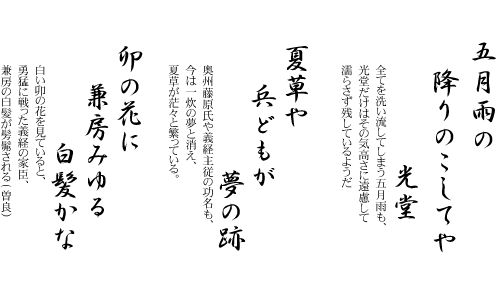
元禄2年1689年 芭蕉46歳の時、門人曽良を伴って5月13日平泉を訪れた。 (その日の夕刻一関の宿に帰り、一関に(5/12・13)2泊、14日朝には出立)
12日一の関に夕方着く。雨強く合羽も通る程也。宿す。
13日天気よし。午前10時頃より平泉ヘ趣く。一里、山の目。一里半、平泉ヘ、 以上二里半というが二里に近い(伊沢八幡は一里余リ奥)。
高館、衣川、衣ノ関、中尊寺、(別当案内)光堂(金色寺)・泉城・さくら川・さくら山(束稲山)、 秀平やしき等を見る・・・・午後4時頃帰る。
宿の主人、風呂を準備して待つ、宿す。
14日天気よし。一の関(岩井郡の内)を立つ。
曽良随行日記より

尚、衣の関は現在の中尊寺入口付近とのこと。
伽羅御所跡→ 柳之御所跡→ 無量光院跡→ 高館→ 衣の関→ 中尊寺→ 金色堂→ 経蔵→ 白山神社→
(曽良日記の泉ケ城までは時間的に無理だったのでは、ないかな?、、)
 |
伽羅御所跡 無量光院の東門に接して建てられていた。奥州藤原氏秀衡、泰衡の居館である 居館の地は今や宅地や畑となり往時を偲べるものは残っていない。 |
 |
柳之御所遺跡 平安時代末期の遺跡。奥州藤原氏の政庁「平泉館(ひらいずみのたち)」跡と推定される。 |
 |
無量光院跡 秀衡が京都の平等院を模して建立した寺院であったが度重なる火災で焼失し今日では土塁や礎石が残るのみ。 2011年世界文化遺産に登録 |
 |
高館義経堂 源義経の最期の場所として知られる。仙台藩藩主により義経堂と義経の木像が建立された。 以降高館義経堂、判官館などと呼ばれるようになる。 |
 |
中尊寺本堂 参道である月見坂を登った右手の中尊寺本坊内にある。中尊寺17院を総括する本堂である。1909年の建築。 |
 |
金色堂 奥州藤原氏初代藤原清衡が1124年に建立したもので 平等院鳳凰堂と共に平安時代の浄土教建築の代表例であり国宝第一号に指定されている。 |
 |
経蔵 金色堂の近くにある。国宝の一切経を納めていた建物で一部平安時代の古材が使用されているが 建築年代は鎌倉末期と推定されている。 |
 |
白山神社能舞台 境内北方に位置する中尊寺の鎮守・白山神社内に建つ。 1853年に仙台藩によって再建されたもの。薪能としても知られている。 |
